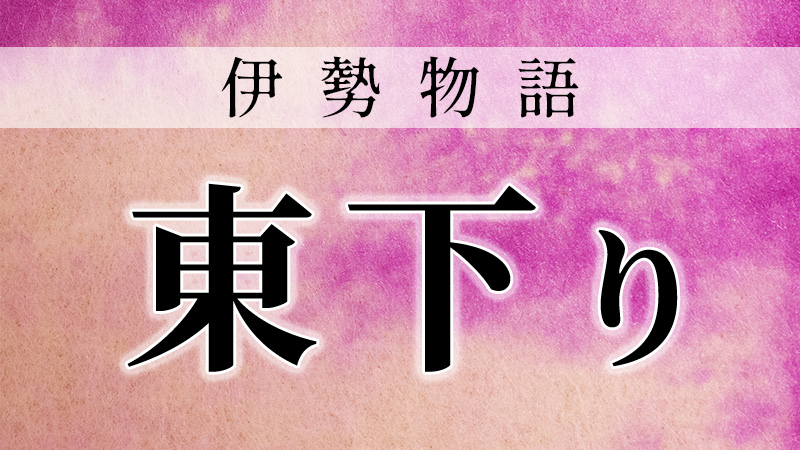
橋を八つ渡せるによりてなむとはどういう意味ですか?
橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。 橋を八つ渡してあることによって、八橋といったのだ。
かきつばたいとおもしろく咲きたりとはどういう意味ですか?
その沢のほとりの木の陰に降りて座って、乾飯を食べた。 ⑦ その沢にかきつばたいとおもしろく咲きたり。 その沢にかきつばたがたいそう美しく咲いていた。
キャッシュ
みな人、乾飯の上に涙落として、ほとびにけり?
有名な「東下り」の第九段に、「皆人、乾飯(かれいひ)の上に涙落としてほとびにけり」《(旅の一行は)皆、(都のことを思って)旅行用弁当の乾したご飯の上に涙を落として(それが)ふやけてしまったのだった》の「ほとび」がそれです。
「えうなきものに思ひなして」とはどういう意味ですか?
役に立たない。 [訳] 自分の身を(世間に)役に立たないものと(ことさら)思い込んで。
「わがうへを思ふなりけり」とはどういう意味ですか?
とよみければ、わがうへを思ふなりけりと思ふに、いとかなしうなりぬ。 と詠んだので、私の身の上を心配しているのだなあと思うと、とてもいとしくなった。
「咲きたり」とはどういう意味ですか?
だから、例にある「咲きたり」は「咲いている」、「思へらず」は「思っていない」だよ。
「まどひいきけり」とはどういう意味ですか?
道知れる人もなくて、まどひいきけり。 以前から友人としている人、一人二人とともに行った。 道を知っている人もいなくて、迷いながら行った。
「思ひなす」とはどういう意味ですか?
おもひ-な・す 【思ひ為す・思ひ做す】
思い込む。 思い決める。 [訳] その男は、自分の身を(世間に)役に立たないものと(ことさら)思い込んで。
「みそかなる」とはどういう意味ですか?
みそ-か・なり 【密かなり】
こっそり振る舞っている。 ひそかだ。 [訳] ひそかに花山寺においでになって。 「みそかなり(みそかに)」は中古の和文体に多く用いられ、漢文訓読体では「ひそかなり(ひそかに)」を用いた。
童べの踏みあけたるとはどういう意味ですか?
童べの踏みあけたる築地のくづれより通ひけり。
子供たちが踏み壊した土塀のくずれた所から通っていた。
水行く川の蜘蛛手なればの現代語訳は?
そこを八橋といひけるは、水ゆく河の 蜘蛛手 くもで なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。 そこを八橋と言ったのは、水の流れる川がクモの足のように八方に流れているので、(それらの八つの流れに)橋を八つ渡してあることから、八橋と言うのだった。
見る 何形?
「見る」は上一段活用です。 して、右の表を見てください。 「み・み・みる・みる・みれ・みよ」と「u」段から上に一段あがった「i」段で活用するので、上一段活用といいます。 (終止形・連体形に「る」、已然形に「れ」、命令形に「よ」を伴います。)
「手をすりて」とはどういう意味ですか?
て【手】 を 擦(す)る
両手をもみ合わせる。 転じて、懇願、謝罪、または畏敬、感謝するさまをいう。
「惑ふ」とはどういう意味ですか?
まど・ふ 【惑ふ】 乱れる。 思い悩む。 迷う。
「おぼしなし」とはどういう意味ですか?
おぼし‐な・す【思為】
① 意識的に、また自分から進んで、そうお思いになる。 思い込みなさる。 ② (上に推測の意を表わす語句を伴って) 推量してある考えをお定めになる。
もの心細しとはどういう意味ですか?
もの-こころぼそ・し 【物心細し】
なんとなく心細い。 [訳] (道は)とても暗く細い上に、つたやかえでは茂ってなんとなく心細く。 「もの」は接頭語。
「あらはなり」とはどういう意味ですか?
慎みがない。 明白だ。 はっきりしている。 [訳] 運命が終わりになることがはっきりしていたので。
「人ま」とはどういう意味ですか?
の解説 1 人のいない間。 人の気づかぬすき。 2 人との交わりが絶えること。
タタラを踏むとはどういう意味ですか?
① たたらを踏んで空気を送る。 ② 勢いよく突いたり打ったりした的(まと)がはずれ、力があまって、から足を踏む。
「踏みあく」とはどういう意味ですか?
ふみ‐あ・く【踏み明く】
[動カ下二]道でないところを踏んで道をつける。
